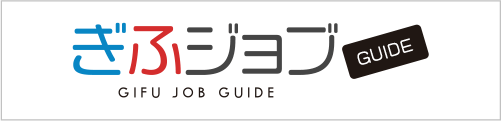受入事業所としてご登録ください!
当協議会では、「インターンシップ受入事業所」としてのご登録を随時受け付けています。ご希望の場合は資料をお送りしますので、事務局までメール、FAX、お電話にてお問合せください。
協議会をご活用ください
ご登録後にご利用いただけるのは下記のような内容となります。
令和5年度にはインターンシップのルールが一部変更となりましたが、そういった話題もメールやセミナー等でご案内するようにしています。
無料で「受入事業所」登録をする場合
- 当webサイト「実習先を探す」への掲載
→年度更新等の案内 - 大学等、高校へ情報発信する場合の一覧掲載等
- (事業所向け)インターンシップ勉強会の案内(無料)
- (夏休み頃)インターンシップ関連アンケートへの協力依頼
→各種調査結果の報告(12月頃)等
登録+入会の場合に追加になること
(年額1口12,000円以上)
- 「実習先を探す」ページ掲載時、画像等の項目が追加に
- 各種印刷物への社名等掲載
- 学生・学校が参加する催しの案内
- 「岐阜県インターンシップ保険」の利用 ※1
※1 詳しくは「保険について」ページをご覧ください。
ご入会もお待ちしております。*岐阜県インターンシップ推進協議会は岐阜県と(一社)岐阜県経営者協会の助成を受け、会員の会費と賛助金で運営しています。ぜひご協賛ください。
初回ご登録の方法
まずは「各種書類」ページから「①webサイト登録方法に関する意向確認書」(Word/PDF)をダウンロードし、記入した後、メールかFAXにて事務局までお送りください。
「自社でのログイン・登録・更新を希望します」を選択された場合は、登録作業完了後、メールにてログインIDとパスワードをお知らせしますので、ログイン(ログインページはこちら)して情報を追加してください。
「申込用紙への書き込みでの登録・更新を希望します」を選択された場合は、「②受入事業所登録 申込書・後半(GICでの登録・更新を希望する方のみ)【Word】」をダウンロードし、記入して事務局までお送りください。
入力した情報は、随時更新が可能です。
新しいプログラムを決定された際や、プログラムの内容が変更になった際などにぜひ更新してください。
また2年目以降は、次年度の情報更新が可能になったタイミングで事務局からご案内します。
【ご注意ください】「インターンシップ」という呼称を使用する条件等
令和5年度より、経済産業省・文部科学省・厚生労働省による「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方(いわゆる三省合意/最初は平成9年に公表)」が改正され、従来のインターンシップがタイプ分けされるなど、条件等が見直されました。
- <タイプ1>「オープン・カンパニー」
企業や業界での説明会的な催し。1day仕事体験等のほか、合同説明会なども含む。 - <タイプ2>「キャリア教育」
大学等と企業等が協働して作る数日程度の教育プログラム。 - <タイプ3>「汎用的能力・専門活用型インターンシップ」
職場で実務を体験するもの。 - <タイプ4>「高度専門型インターンシップ」
主に大学院生を対象とした、高度な専門性を要求される実務を職場で体験するもの。
※この中で「インターンシップ」という呼称を使えるのは<タイプ3>、<タイプ4>のみとなります。
さらに、「インターンシップ」の実施には下記のような条件を満たすことが求められます。
- (就業体験要件)学生の実習期間の半分を超える日数を職場での就業体験に充てる。
- (指導要件)就業体験では、職場の社員が学生を指導する。また、実習終了後には学生へのフィードバックを行う。
- (実施期間要件)<タイプ3>は5日間以上、<タイプ4>は2週間以上
- (実施時期要件)学業との両立の観点から、学部3年・4年ないしは修士1年・2年の長期休暇期間(ただし大学の正課等の場合は限定されない)
- (情報開示要件)学生が実習を計画する際に選定基準となるような情報をHP等に掲載する。
→プログラムの趣旨、実施時期・期間、場所、募集人数、選抜方法、就業体験の内容、体験に必要とされる能力、フィードバックについて、当該年度のインターンシップ実施計画、過去数年間の実績概要 など
→採用活動開始以降にインターンシップを通じて取得した学生情報を活用する場合はその旨
※協議会ではタイプに関わらず学生の企業研究に役立つ情報全般を掲載しています(ただし有償インターンシップは除く)。学生がインターンシップを計画する際に参考になる情報を掲載していただくようお願いいたします。ご不明な点は事務局までご相談ください。
よくある質問
職場体験のため、報酬は不要です。
インターンシップは、事業所・学生の双方にとって無償の制度です(報酬が出る場合は、インターンシップに特化した保険の対象外になることがありますので、ご注意ください)。
無償ではありますが、学生の主な目的は就業体験(=正社員としての体験)です。決してアルバイト的な仕事や社内の見学等に終始することなく、できるだけ幅広い体験、交流ができるような配慮をお願いします。また、あくまで体験ですので、過度の残業が生じるような課題・日程は避けるようにしてください。
学校の授業や試験等がない時期をおすすめしています。
学生にとっての優先事項は、本分である学業です。そのため、長期休暇となる夏季や春季を利用しての実施がおすすめです。
正確な日程は学校により異なりますが、夏季休暇は8月中旬~9月初旬頃、春季休暇は2月中旬~3月頃とする場合が多いようです。
またその他の時期であれば、授業がない曜日や時間帯に実施するなど、学生への配慮をお願いします。
事業所負担でも、学生負担でもかまいません。
交通費の支給や昼食の提供、宿泊時の寮等については事業所にお任せしています。制服の貸与なども、実習内容に応じて判断してください。
ただし、当初予定していた実習先から出かける必要が生じる場合や、特定の服装で出勤するために費用が発生する場合などは、できるだけ事業所で負担するなど、学生に大きな負担がかからないように配慮をお願いします。
※インターンシップに必要となる費用を助成している自治体もあります。協議会で把握している取り組みは、「おすすめリンク」ページでご紹介しています。
幅広い体験・交流の機会を作ってあげてください。
実習日程については「受入事業所を探す」ページで様々な事業所の内容もご覧いただきながらご検討ください。「働く」とはどういうことか実感できるよう、職場の見学だけでなく実作業を盛り込んだり、様々な部署の先輩と話す時間を設けるといった工夫をお願いします。
また、社内にインターンシップの経験者がいる場合は体験談を聞いたり、実習に来た学生にアンケートに答えてもらったりすることも参考になります。
実習内容の一例
- 業務内容などを理解するためのオリエンテーション
- 業務に必要なマナーの研修
- 改善点を見つけるなどの課題を与えての見学・実作業
- 先輩社員たちとのランチタイムや座談会
- 他大学の学生とのグループワーク
- 上司等も出席する成果発表会
※コロナ禍以降、オンライン開催の実習も出てきています。遠方に住んでいる等、交通面でハンディのある場合でも参加しやすいというメリットもあります。なおこの場合も、学生が仕事や業界を身近に感じられるような工夫をしていただきますようお願いします。
(学校によっては、オンラインプログラムは単位認定の対象外とするケースもあるようですので、注意が必要です)
協議会では、各種会議など交流していただく機会を作っています。
総会をはじめとして、協議会では様々な催しを開催しており、その際にはできるだけ情報交換や名刺交換の時間を設けています(ハイブリッド開催となっている催しもあります)。会員企業、協力員、登録のある受入事業所の皆様には郵送、メールでお知らせしていますので、ご活用ください。なお開催したイベントの様子については、TOPICS等でご紹介しています。
また、毎年継続して様々なアンケートも行っています。お手元に届いた際には、ぜひご協力ください。
※今後インターンシップを検討される上で、催しの見学等をご希望の場合は、協議会までお問合せください。
開催行事の例
- インターンシップ合同説明会(会員企業・協力員限定)5~6月
事業所が個別ブースを設け、主に夏休みにインターンシップを希望する学生に直接説明する会です。 - 理事会・総会 6月
総会と併せて、インターンシップに関する講演会や事例発表会を実施しています。 - 推進会議(会員企業・協力員限定)12月頃
学校・事業所双方が情報交換する会議です。 - インターンシップ勉強会 年1~2回
インターンシップ受入計画のある企業・団体向けのセミナーです。